–肉離れ受傷後–
所見なし
強度を上げていく
また離れた
どれだけ注意深く所見を見極めて、リハビリで機能が改善したと思っても
スポーツ復帰をすると再発してしまうことも多々ある病態です
病態を把握しているようでできていない 肉離れの所見ですが
どうやら損傷部位による影響もあるようです
平均年齢26.4歳、プロアスリートの集団を中心に対象とした報告を共有します
この記事のポイント

- 大腿二頭筋のTジャンクション損傷は、106件のうち57件で再損傷が生じました
- 経過を追うことができた57件のうち44件の再損傷時の重症度は、以前の損傷よりも高いグレードは22件、同じグレードは16件、低いグレードは6件でした
- 経過を追えた57件のうち45件では、34件が3か月以内に再発し、40件が12か月以内に再発していました
文献情報
大腿二頭筋の遠位筋腱Tジャンクション:MRIのケースレビュー
Entwisle T, Ling Y, Splatt A, et al.” Distal Musculotendinous T Junction Injuries of the Biceps Femoris: An MRI Case Review” Orthop J Sports Med. 2017 Jul 20;5(7):2325967117714998.
抄録和訳
背景
大腿二頭筋の遠位筋腱移行部T字ジャンクション(DMTJ)の損傷は、複雑な筋の解剖構造および筋の二重神経支配が影響し、他のハムストリング損傷とは異なる経過を辿り、この損傷は別の病態と捉える
この領域の損傷は、長期のリハビリテーション期間を設けるにもかかわらず、特に高い再発率を示す
目的
大腿二頭筋のDMTJの解剖を解明し、MRIにて認められる損傷パターンを分析することで予後およびリハビリテーションの一助とし、再発のリスクを最小化すること
方法
同一の施設における、55名、106件のMRI検査から、大腿二頭筋DMTJの急性損傷を対象とした
DMTJ損傷は、長頭、短頭、または両方として分類され、それぞれの損傷程度は個別にグレーディングされた
以前のMRIでDMTJの急性損傷の既往、または急性損傷部位に瘢痕を認めた場合に損傷は再発と分類した
結果
106件の大腿二頭筋DMTJ損傷のうち、長頭の単独損傷が51%、両方が関与した症例は約43%、短頭の単独損傷は7%だった
本研究におけるDMTJ再損傷の再発率は54%だった
再発57例中45例では以前の損傷日を把握しており、そのうち34例(76%)が3か月以内に再発し、40例(89%)が12か月以内に再発していた
再損傷は44例中22例(50%)で以前の損傷よりも高いグレードであり、16例(36%)は同じグレード、6例(14%)は低いグレードだった
したがって、再発損傷の86%は以前の損傷と同等またはそれ以上のグレードだった
結論
本研究より、大腿二頭筋DMTJ損傷のような高リスクの筋損傷は、損傷部位を特定し、損傷の範囲と損傷度を評価するためにMRIを用いることが推奨される
マイルの推し文(POWER SENTENCE)
In our experience, injury to the DMTJ becomes relatively symptom free 3 to 4 weeks after the initial injury (pain-free full range of motion and with sport-specific activities), but the scarring at the epicenter of the injury remains as an intermediate-to-low signal on MRI, suggesting immaturity.
我々の経験では、DMTJ損傷はおおよそ受傷後3〜4週で症状がなくなるが(フル可動域、スポーツ特有動作で痛みなし)、損傷部位の瘢痕はMRI上、比較的高輝度な信号を出しておりまだ成熟していないことが考えられる
感想にまいる
ハムストリングスのTジャンクション損傷
あまり馴染みのある名称ではないかもしれません
2017年に発表された報告とはいえ、恥ずかしながらマイル自身もあまり馴染みのないワードでした
ハムストリングスの損傷はLプロトコルに代表されるように、炎症期の所見が落ち着いてきたら適切な負荷での伸長ストレスをかけることと、筋損傷の分類を理解し適切な復帰までの期間を設けることが大事という知見をもとにリハビリを行なっていましたが、
ハムストリングスの損傷部位を把握することも欠かせません
The 2 heads of the biceps femoris are innervated separately and have differing force vectors due to their separate sites of origin. The different force vectors converge across the DMTJ and likely contribute to the increased rate of injury and recurrence seen in this region.
大腿二頭筋の2つの頭は別々の神経支配を受けており、それぞれの起始部が異なるため、異なる力のベクトルを有する
異なるベクトルはTジャンクション(DMTJ)を横断して収束するため、この部位の損傷および再損傷の高い発生率につながる可能性が高い
この論文中の図1はぜひとも見ていただきたい図です!!!
バルセロナのMLG-R分類ではlocationの記載があり、ざっくりと近位、中間、遠位と分類されていました
損傷部位で大腿二頭筋の遠位に圧痛を認める場合、Tジャンクションの損傷を確認することはリハビリの進め方を考えていく上で重要です
論文中でも
We found that 86.4% of recurrent injuries were of the same or higher grade than the prior injury and that 68.2% of grade 2 injuries were recurrent and 71.4% of the grade 3 injuries were recurrent. These results support the idea that recurrent injuries tend to be of greater severity than the index injury.This may be due to an underestimation of the extent of injury, an early return to full training, and/or inadequate rehabilitation.
再発例の86.4%は損傷程度が同じあるいは重度であり、グレード2の68.2%とグレード3の71.4%が再損傷をしていたことが分かった。これらの結果は、再損傷は初回損傷よりも重症度がより高くなるという考えを支持している。 (再損傷は、)損傷の範囲を過小評価したことと、早期のトレーニング復帰、不十分なリハビリテーションのために生じたと考えられる
このように、損傷部位を把握し復帰を安易に進めないことがTジャンクション損傷においては重要です
他のハムストリング損傷のように、時期と所見を合わせて強度を上げていくのではなく、症状が良くなっていたとしても完全復帰をするまでに強度のあげ方のコントロールや復帰期間の考慮をすることが必要ですね
この論文では、MRIで瘢痕組織の成熟度の経過を追うことが望ましいと報告されています
ハムストリングス損傷のⅡ型と診断が出た場合でも、実際の損傷部位はどこなのかをしっかり把握することが大事です
大腿二頭筋遠位の症状があった場合は、Tジャンクション損傷のことも頭の片隅に入れて、所見が3~4週で無くなっても油断せずにリハビリに取り組んでいきたいです
関連記事










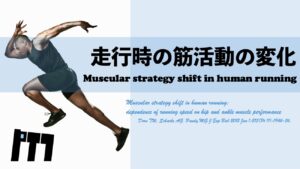

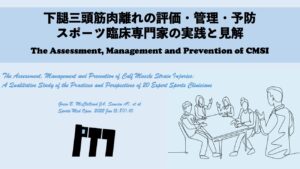
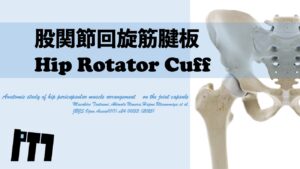
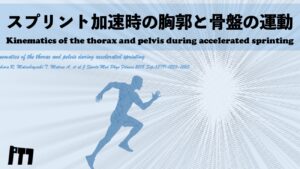
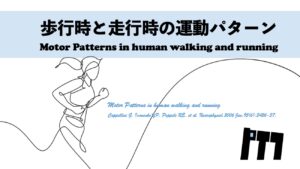
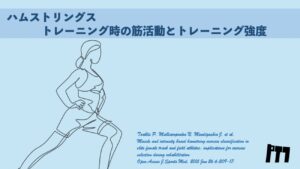
コメント