全身の筋が上手に働くことで「走る」という動作が可能になりますが、全身の筋を意識的に動かして走る人はいないかと思われます
私たちは「走る」という意思を持って走りますが、その時に身体ではどのような反応が起きているのでしょうか
走行時の筋活動を分析してみると、
どうやら、ある程度パターン化された筋活動の波形を確認することができるようです
「走る」ために、脳から体へ信号がパターンとして伝えられ各筋が協調的に働くことで走るという動作を実現することができているという報告です
この記事のポイント

- 8名の健常な被験者を対象に、3〜9km/hの歩行と5〜12km/hの走行をしてもらいその時の筋活動、3次元動作解析、床半力のデータを集めました
- これらのデータを分析すると、歩行と走行時に1周期内で5つの波(component)があることが分かりました
- 歩行と走行の違いを調べたところ、走行では歩行と比較しcomponet2の出現タイミングが早くなることが分かりました
- また、componentを構成する下肢の筋には歩行と走行で大きな変化はありませんでした
文献情報
歩行時と走行時の運動パターン
Cappellini G, Ivanenko YP, Poppele RE, et al.” Motor Patterns in human walking and running” J Neurophysiol.2006 Jun;95(6):3426-37.
抄録和訳
背景
歩行と走行の間には明らかな違いがあるにも関わらず、この2つの人間の移動様式は、共通のパターン生成ネットワークによって制御されている可能性が高い
しかし、歩行と走行の運動学的および運動力学的な違いを考えると、歩行と走行に対応する筋活動もかなり異なっている可能性が考えられる
目的
片側の四肢および体幹の32の筋における運動学データおよび筋電図(EMG)活動を記録して、歩行(3,5,7,9km/h)と走行(5,7,9,12km/h)を各速度でも比較し、歩行と走行の違いを調べること
(8名の健康な被検者を対象に実施、被検者は3~12km/hの速度でトレッドミル上を歩行または走行した)
結果
筋活動のタイミングは、以前我々が歩行で見出したのと同様に、走行においても5つの基本的な成分によって説明された
各成分は、下肢筋では歩行と走行において似たような群で負荷がかかっていたが、上部体幹の筋では異なる筋群に負荷がかかっていた
歩行と走行の間の主な違いは、立脚期に生じる1つの成分が、走行周期においては歩行周期より早い位相へと移動していた
これらの歩容間の筋活動の違いは、歩行と走行を同じ速度範囲(5–9 km/h)で記録した結果から示されるように、単純に移動速度に依存するものではなかった

考察
この結果は、歩行と走行の運動プログラムが遊脚期の筋活動を構成する部分と、立脚期および立脚期から遊脚期への移行中の筋活動を構成する2つの部分から成っていることを裏付ける
歩行と走行の間での成分のタイミングのずれは、歩行と走行における立脚相の相対的な持続時間の違いを反映している
マイルの推し文(POWER SENTENCE)
We expected though that running, which places different biomechanical demands on the neuromuscular system, would exhibit different muscle activation patterns. However, many muscle activation patterns were quite similar to those observed during walking.
(前文で、歩行において3km/hの速さから速度を上げた歩行を比較しても筋活動のパターンはほぼ変わらないことを説明)
(歩行と)異なる神経システムを必要とする走行は、筋活動が異なるかと思われた
しかし、走行時の大多数の筋活動パターンは歩行で観察されたものと非常に類似していた
感想にまいる
抄録を英訳しても理解しにくいので論文のまとめをしながら、感想もお伝えします
この論文のIntroductionに、動物実験から得られた知見が紹介されています
猫において、中脳の歩行領域(MLR:mesencephalic locomotor region)への刺激強度を増すだけで歩行速度が上がり、さらに強い刺激では、トロット(速歩)からギャロップ(スプリント)へと歩容を変化させた
生物において、歩行や走行をするためにパターン化された中枢からの下行性プログラムがあるということは推察されていました
しかし、歩行から走行へと移動形態が変わった時に中枢からの下行性プログラムの内容は各形態で類似しているのか異なるのかという疑問に対して研究した論文です
歩行から走行へ移動形態を変えることは、動作自体が異なるため、走行時に働く筋や筋発揮のタイミングなどが大きく変化することが考えられていました
しかし、この研究を通して、歩行でも走行でも使われる筋活動のパターンはそんなに変わらないということが分かりました
歩行時と走行時の32の筋の使い方を速度別に示された図をご覧ください

図は各筋の歩行または走行の1周期でのEMGの波形を示しています
歩行と走行で波形の大きさ(=筋出力)は変わりますが、下肢筋のうち腓腹筋内側頭(MG)以下の遠位筋で走行時の筋発揮タイミングが早期に変化する様子が見てとれます
これら32筋の表面筋電図の波形を時間軸に基づいて分析すると、歩行でも走行でも周期内に5つの波(component)が出現することが分かりました(下図)

この5つの波を5~9km/hの歩行と走行で比較したところ、走行ではcomponent2のタイミングが速くなっただけでcomponent1,3,4,5のタイミングは歩行時とほぼ一致していました
時速7kmの歩行と走行の各componentの構成を比べても下肢の筋は歩行時と類似していることが分かります

脳や中枢神経が、これら5つのcomponentを使って、多くの筋をコントロールすることで歩行や走行が実施されている可能性があります
我々は、歩行と走行は運動学的に別のものと捉えてしまいます
しかし、筋出力の違いはあれど賦活する筋はほぼ同様で、component2 の筋発揮のタイミングが早期に起これば歩行から走行へと変化するという知見は興味深いです
これらの知見から
やはりセラピストとしては、パフォーマンスアップのために筋肉のみを鍛えるのではなく動作にもフォーカスをしていく必要があるということですね
筋肉を鍛えれば速く走れるわけではないし、野球が上手くなるわけでも、サッカーが上手くなるわけでもありません
しかし賦活できる筋がないと動作のcomponentをそもそも構成することができません
もちろん、動作に必要な可動域がないとそもそも動くこともできないですね
運動センスと言われるものは、componentを構成する筋が十分にあること、動作ができる可動域があることを前提にcomponentの発揮タイミングが協調的に行われることが大事なようです
私自身、スポーツに打ち込んでプロ選手になりたいと夢を見る時期がありました
しかし、打ち込めば打ち込むほどトップレベルとの差を痛感し、どうすればこの差を埋めることができるのか分かりませんでした
だから、身体を扱う専門家になって運動センスの本質を知りたいという気持ちもあってこの道を志しました
動作周期での動作解析と筋電図を分析することにより、componentを出現させることで筋発揮のタイミングやその時の構成筋を分析することが運動センスという本質に近づく一つの手段になるかも!?
と感じさせてくれるような論文でした
ただ、この論文でのデータの分析方法が難しすぎて私はマイってしまいました…
関連記事


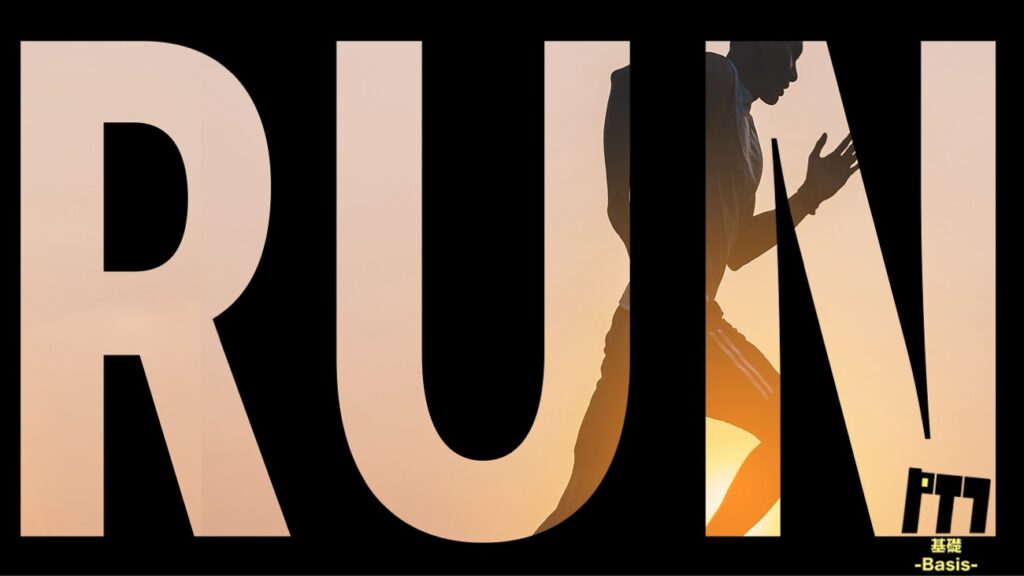








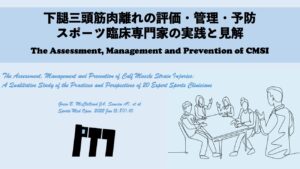
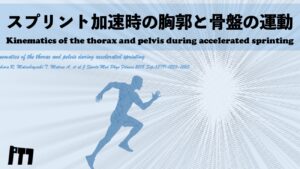

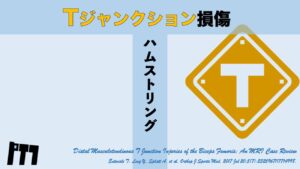
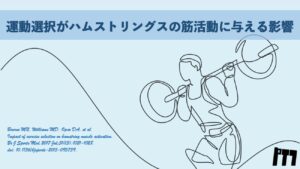
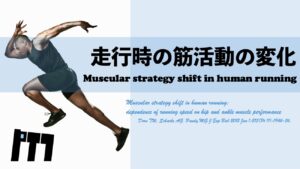
コメント