実際にチーム帯同でACL損傷が起こった後に、理学療法士やスポーツトレーナーが行う受傷後の対応と
病院受診から手術決定までの流れをお送りしていきます
この記事のポイント

- ACL損傷を疑われる怪我が起こった場合は、救急対応をしたのち病院へ受診誘導をします
- 病院では、各検査を行い病名の確定診断後、手術決定となります
- 各章でどのような対応が行われているのかを発信していきます
ACL損傷後の対応
ACLはスポーツ中に起こることがほとんどなので練習や試合現場を想定して考えます
様々な受傷シーンを把握し、スポーツ現場に帯同した際に同じようなシーンに遭遇したら…というイメージを持って記事をご覧ください
ACL損傷時のシーンはYouTubeで見ることができます。
損傷直後の対応
選手の元へ駆け付けてから問診を行います
実際の受傷シーンを見ていればある程度の怪我の種類を想定しながら選手の元へ向かいますが、決めつけてはいけません
私もトレーナーで現場対応をした際に、ある程度病態を決めつけて救急対応をしたら、実は違う怪我だったという経験もあります
こればかりは経験やタイミングも物を言いますが色々な引き出しを持ってたくさんのシミュレーションをしておく必要があります
問診では以下のような内容をチェックします
- 受傷時にゴリ音、ブチっとなった感じがあるか
- 痛くて荷重困難、荷重をすると膝が抜ける感じがあるか
- プレー継続できそうか
基本的には、ゴリと鳴った感じがあり痛みが強いとその場ですぐプレー中断、
試合であれば交代、練習であれば離脱とします
しかし、その時にACL損傷をしていても荷重ができて、プレーもできそうという選手も一定数います
私も、試合中に選手が怪我をして対応した際、受傷シーンの直後はプレーできると判断してピッチに戻しても、その後何気ないプレーで膝崩れが生じて選手交代
その後、病院検査をしたらACL断裂だったという経験もしたことがあります
その時の対応を何度も省みますが、選手状況を瞬時に判断しプレーを継続するのかしないのか、
ベンチに入っているスタッフとどのようなやりとりをするのか、ということを
スムーズにできるようになるためにはまだまだ時間がかかりそうです
問診をしたら理学所見と徒手検査を実施します
理学所見と徒手検査
- 視診、触診
- Lachmanテスト ※選手によっては痛みで力が入り検査困難な場合もあり
- 前方引き出し ※同様
- N-test ※難しい
- 膝関節 外内反ストレステスト
- McMurrayテスト ※痛みがある時は精査困難
受傷直後のチェックは、特に痛みが強い選手に対しては徒手検査を行うことは困難です
うまく力が抜ける選手は受傷直後でも徒手検査で判断をすることができるかと思います
受傷直後に大事なことは問診して選手の様子や雰囲気を感じる、患側に体重をかけることができるか、ジャンプやダッシュ、切り返しなどの動きをすることができるかどうかのチェックです
これらのチェックをしてACL損傷の可能性が高ければ、プレーをストップさせピッチの外へ選手を出して受傷後の対応をします。
ピッチの外へ出る選手は、担架で運ばれる選手もいれば自力で外へ出ることができる選手もいますし、手引き歩行やおんぶをしてピッチの外まで運ばれる選手もいます
離脱後の対応
ピッチの外へ出て安静にしていると数分後から関節内の水腫(血)が生じて膝がパンパンになる選手もいれば、疼痛が落ち着いてくると荷重もできるし、腫れもそんなに出ない選手もいます
これらの違いは明確なことは分かりませんが、
実は昔にACLを部分損傷をしていて靭帯が弱かった!?…などの影響も考えられます
シーズン前に選手のフィジカルチェックとして徒手検査を行っていた時期がありますが、Lachmanテストで脛骨の前方移動量に左右差がある選手は一定数いたので、なにかしらの関係性はあるような気もしますがどうなんでしょう…?
ピッチ外に出たら、まずはRICE処置を行います
- Rest 局所安静
- Ice アイシング
- Compression 圧迫
- Elevation 挙上
RICE処置をしている時は時間が比較的あるので選手と話しながら、病院受診の誘導をします
私は、病院勤務でチームドクターとすぐにコンタクトができる環境だったので、直接ドクターに連絡し診察の手配をしていました
処置を行い落ち着いてきたら、松葉杖を用意して選手へお渡しします
もし軟性装具など膝を固定できるものがあれば尚更良いですね
ちなみにですが、最近はRICEではなくPEACE & LOVEという概念も出てきています
- Protection 保護
- Elevation 挙上
- Avoid anti-inflammatories 抗炎症薬を避ける
- Compression
- Education 教育
&
- Load 負荷
- Optimism 楽観思考
- Vascularisation
- Exercise 運動
PEACE&LOVE
確かに大事です
病院受診 診察〜手術決定
徒手検査やMRI検査を行い
必要があれば穿刺を行いその時の関節液の状態もチェックします
検査の結果、ACL断裂を認めたら、基本手術療法が選択されます
年齢や、既往歴を考慮して手術ができない方もいるので、その場合は保存療法が選択されます
まだ、骨端線が成熟していない子供や手術をすることにリスクのある疾患を合併している場合は保存療法です
また、数ヶ月後に学生生活最後の大会を控えている、自分の人生を賭けた試合があるというような強い希望がある方に対しては受傷後5~6ヶ月程度、リハビリを経て経過良好であれば保存療法で復帰を目指す場合もあります
私もそういう方のリハビリを実施して最後の大会にラスト10分出場という目標を共に達成した症例もいます
その方は、大学ラガーマン
学生最後の大会出場後ACL再建術をして競技は引退され、社会人として生活を送られています。
ACL再建手術の待機期間
プロアスリートの場合受傷後、超早期の手術を行う例もあります
横浜F・マリノス
宮市選手の場合
7月27日受傷→8月2日手術(待機期間:6日)


アルビレックス新潟
高木選手の場合
9月18日受傷→9月30日手術(待機期間:12日)

コンサドーレ札幌
深井選手の場合
9月18日受傷→9月25日手術(待機期間:7日)


受傷から手術までかなり速いスピード感で方針が決定されて治療が進んでいると感じられますね
ACL損傷後早期の手術に関しての報告がありますので共有します
Yuki Yamanashi先生の論文
[Safety and Early Return to Sports for Early ACL Reconstruction in Young Athletes: A Retrospective Study] にて
術後早期のACL再建術において、受傷後1週以内に手術を行なったグループでも他のグループと比較して優位な合併症の増加は見られなかったと報告されています

Gustavo Gonçalves Arliani先生の論文
[Treatment of Anterior Cruciate Ligament Injuries in Professional Soccer Players by Orthopedic Surgeons] にて
ブラジルのサッカー選手に対して受傷後1~4週以内で手術を行い90%が復帰できたと報告されています

ACL損傷受傷後早期の手術は、結果として早い競技復帰に繋がることがあるので、プロアスリートなどは早期に手術することもあるようです
しかし、
手術は早ければ早い方が良いという訳ではありません!
基本的には、患部の炎症が治り可動域、筋力、日常動作が改善することを目標として術前リハビリを行います。
次は術前リハビリについてをご覧ください
関連記事








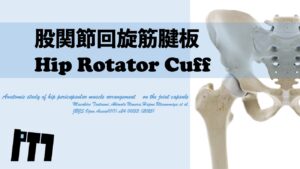




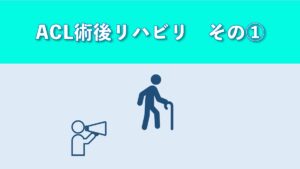


コメント