肉離れといえばハムストリングス
ハムストリングスの肉離れも厄介な経過を辿る症例もあります
今回はハムストリングス肉離れのリハビリに臨むにあたり押さえておきたいポイントについてお送りします
ハムストリングスの解剖
大腿二頭筋(BF:Biceps femoris)
起始停止
坐骨結節
↓
大腿骨祖線外側唇−腓骨頭
支配神経
長頭(BFLH):脛骨神経 (L5~S2)
短頭(BFSH):総腓骨神経 (L5~S2)
半腱様筋(ST:Semitendinosus)
起始停止
坐骨結節
↓
脛骨粗面内側
支配神経
脛骨神経 (L5~S2)
半膜様筋(SM:Semimembranosus)
起始停止
坐骨結節
↓
脛骨内側顆、斜膝窩靭帯、膝窩筋筋膜、膝後方関節包、後斜靭帯、内側半月板
支配神経
脛骨神経 (L5~S2)
ハムストリングス損傷の割合
Grangi先生が
[Location of Hamstring Injuries Based on Magnetic Resonance Imaging: A Systematic Review] にて
計2761件の急性ハムストリング損傷のうち、最も頻度の高い損傷は大腿二頭筋長頭(BFLH)(69.8%)であり、次いで半腱様筋(ST)(15.4%)、半膜様筋(SM)(13.1%)、大腿二頭筋短頭(BFSH)(1.7%)だった
と報告されています
病院やクリニックで勤務している場合は、MRI検査前のハムストリングス損傷症例を見る時、
チーム帯同している際は、ハムストリングス受傷後をチェックする時に、
「ハムストリングスのどこが損傷しているか?」
を把握する際、頭に入れておきたいポイントです
ハムストリングス損傷の部位
近位付着部損傷の分類
| 損傷部位 | 名称 | 備考 |
| SM | SM単独 | 保存適応 |
| SM+BF+ST | 総腱 | オペ適応 |
| BFLH+ST | 共同腱 | 場合によってはオペ適応 |
| ST | ST単独 | 滅多に生じない |
付着部の損傷が疑われる際は、損傷部位によって保存療法か手術適応か分かれることがあります
頭の片隅に入れて受傷後の対応やリハビリテーションに臨みたいですね
股関節屈曲、膝伸展(ハムストリングスの最大伸長位)での受傷は、
ダンサーに多く発生しており、半膜様筋での損傷が多く、近位腱の部位で損傷が多いと報告されています
参考文献
また、同様の姿勢をとる頻度が多いレスリングおよび柔道選手を対象に行なった調査でも、近位付着部損傷のうち約80%がSM単独損傷との報告があります
参考文献
中嶋耕平:ハムストリング付着部-レスリング. 臨床スポーツ医学 ,42(2):178-183, 2025
中央部の損傷、遠位損傷
筋の中央や遠位の損傷の場合も圧痛を把握し、筋実質あるいは筋内腱周囲の圧痛があるのかを把握して経過を追うことが重要です
遠位外側に圧痛がある場合は、Tジャンクション損傷の可能性も考慮したいです
ハムストリングス損傷後の経過
JISS分類で損傷度を判別することで大まかな復帰時期が決まってきます
ハムストリングス損傷の特徴としては
大腿二頭筋の損傷のうちT ジャンクションと言われる遠位筋腱移行部の損傷は、構造的な特徴や二重神経支配の影響で予後が悪いと言われており高い再発率が指摘されています
また、Free tendonの損傷は56日と長い経過を辿ることが報告されています
ハムストリングス損傷のオペ適応
トップアスリートで、筋腱の短縮を伴う坐骨付着部近くの共同腱または総腱の完全断裂、付着部完全剥離は保存療法でパフォーマンスを回復することが難しく受傷後2週以内に手術をすることが望ましいとされています
受傷後2週以上経過すると腱断端の短縮や坐骨神経など周囲組織と癒着も生じ修復操作が難しくなるため、早めの判断が必要です
この重症度の損傷であれば、基本的に病院受診をするかと思われますが、チーム帯同などをしている際にも早期の病院受診を促した方がいいかと思われます
ただし、半膜様筋のⅢ型損傷は保存療法で復帰可能とされています
また、レクリエーションレベルでは保存療法でADL復帰、スポーツ復帰可能です
参考文献
仁賀定雄, ほか : ハムストリング付着部損傷の手術. 臨床スポーツ医学, 34(8):796-803, 2017
参考文献
吉村英哉, ほか:ハムストリング付着部損傷の手術療法. 整形・災害外科, 63(4):391-398, 2020
私自身も、60代のレクリエーションレベルでの長距離ランナーの方で共同腱断裂を受傷された方に対して保存療法でハーフマラソンに復帰された方を経験したことがあります
肉離れプロトコル

L-protocol →ハムストリングス伸長位での遠心性収縮を目的としたエクササイズ
C-protocol →ハムストリングス伸長位を強調しないエクササイズ
参考文献
Askling CM先生が
[Acute hamstring injuries in Swedish elite football: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols] にて
MRIでハムストリングス損傷と診断された75人のスウェーデンのエリートサッカー選手を対象にリハビリプロトコルをLプロトコルとCプロトコルにランダムに群分けして復帰期間を追った研究では、
Lプロトコルが28日、Cプロトコルが51日と優位にLプロコトルで復帰期間が短かった
また、スプリント受傷、ストレッチ受傷のタイプ別で群分けしてもLプロトコルで優位に復帰期間が短かったと報告しています
L-protocolのメニューはリハビリでもぜひ取り入れたいメニュー項目です
また、リハビリを行う上でハムストリングスの筋活動を把握していることも大事です
復帰基準
肉離れの明確な復帰基準が確立されているとは言い難いです
ですが、サッカーにおいてハムストリングス肉離れ後の競技復帰に関してFIFA(国際サッカー連盟)が実施したデルファイ研究を紹介します
FIFA consensus statement
FIFAが主催したアンケートを基にしたオンライン調査で、競技復帰(RTP)の明確な定義と医学的基準を定め、さらにハムストリング損傷後のRTPに関する責任の所在を明らかにすることを目的とした報告


RTPの決定には、選手本人、スポーツドクター、PT、フィジカルトレーナー、コーチ(監督含む)が共通の意思決定に基づいて行う必要があるとされています
ただし、最終の責任所在はスポーツドクターを推奨されています
RTPの基準は、メディカルで競技復帰の許可が出た上で選手が試合やトレーニングのフル合流に臨むメンタル的な準備ができていることとされています
RTPの基準に含まれる可能性のあるものとしては上図の推奨項目をご参照ください
フィールドテストでは、反復スプリントテスト(RSA:Repeated sprint ability)や片足ブリッジ(single leg bridge)、減速ドリル(deceleration drills)が推奨されています
また、ポジション特性、試合特性を考慮したGPSを利用する評価も推奨されています
GPSを利用することで、走行距離やスプリント回数、加減速の速度、回数などデータを見ながら選手の特性に合わせて強度を上げていくことができますね
RTP基準から除外するものには、MRIが挙げられています
MRIに頼りすぎると良くないということを示しているのでしょうか
しかし、論文によってはMRIで経過を把握しておくことが望ましいとされている場合もあります
ですので、肉離れ後の競技復帰としては、MRI所見のみならず理学所見や各競技フィールドでのパフォーマンステストも需要になります
肉離れの競技復帰に関しての方針は、医師を中心とした各スタッフの評価も考慮することが重要です
論文内で示されていたクリニカルテストに上げる項目で支持率の高かったフィールドテストの項目は以下の通りです

H-testは以下の動画を参照にしてください
ハムストリングスの復帰判断は難しいですよね
前提としてハムストリングスの損傷程度を把握していることが重要ですが、
例えば画像上クリアで、診察では強度を上げていきましょうとなっても選手の感覚に違和感が残っていたりする場合もあります
違和感が残っていても、今週末に欠かせない試合があるから今日の練習に合流しないといけないとか、
明日の試合が自分の人生を大きく左右する大事な試合だとか…
その時の様々な選手状況やチーム背景も考慮して、目先の試合に強引にでも間に合わせるのか
あるいは、再発を避けるために症状が残っているのであればもう1週復帰を延期するのか
など、現場レベルではその駆け引きが非常に重要です
試合、練習復帰を許可して問題なければ最高ですが、また再発をしてしまうこともあります
再発をすると、選手が苦しむことはもちろん、選手との信頼関係、他のスタッフとの信頼関係の問題にも発展することもあります
そういう意味でも、肉離れは、スポーツ障害で多く発生し、
再発も多い障害なので選手、スタッフを悩ませる怪我の1つに挙げられます
選手が復帰する or しない の駆け引きを上手くするために、
セラピストはたくさんの引き出しを持っておかなければなりません
教科書的な知識はもちろん必要ですが、そこだけに拘ることも良くないです
筋損傷後の復帰時期も、あくまで目安なのでその時期が経過したらOKという訳でもありません
ハムストリングスについての様々な知識・経験を武器にして、リハビリに臨むことで適切なRTPの達成につながるのではないでしょうか
ご覧いただきありがとうございました
ハムストリングスの肉離れのリハビリテーションの参考にしてみてください
関連記事









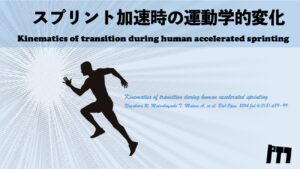

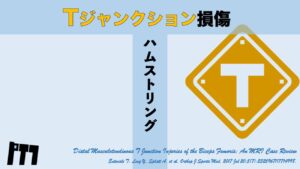



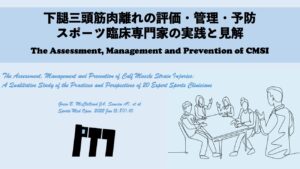
コメント